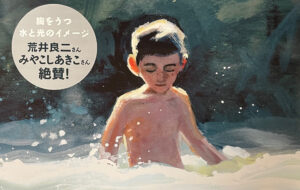廣瀬カウンセリングについて
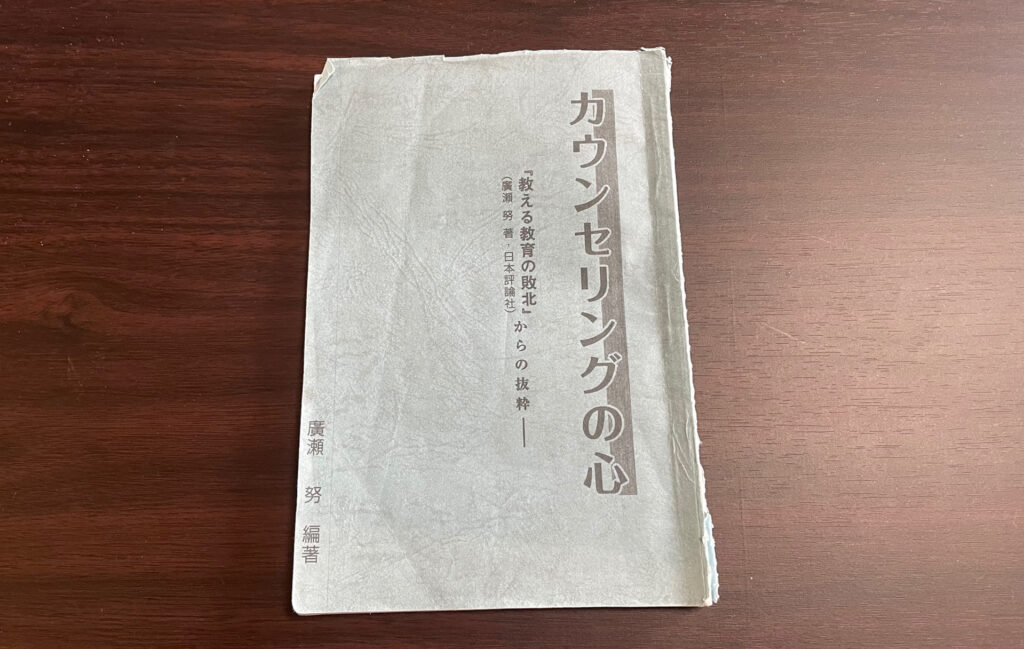
私が入会してから修了するまで。
今回は私がカウンセリングを学び、原点にもなっている廣瀬カウンセリングについて書きます。
普段X(Twitter)やblogでは「廣瀬カウンセリング」の名前を出来るだけ出さないようにしていますが、
それは、カウンセラーとし独立し、自由な立場で発信しているので、廣瀬カウンセリングに迷惑をかけてはいけないと思うからです。
この投稿も、あくまで現在の私の立場からの廣瀬カウンセリングについてなので、正確には直接調べていただきたいと思います。
私が教室に入会したのは、2011年でした。
そのころはまだ廣瀬先生はご存命でカウンセリングをしていらっしゃたので、
直接カウンセリングを受けられた最後の世代です。
実は、私はそのころ吃音はそれなりに改善していて、言い換えは多用していましたが、
普段はそれほど話すことに支障はありませんでした。
ただ、音読だけは相変わらず苦手で、数人が相手でも,よくどもっていました。
普段は一見流暢なだけに、余計に恥ずかしかったですね。
カウンセリングの内容についてはほとんど分かりませんでした。
最初は、カウンセリング後に、呑みに行くのが楽しみだったから、参加していたようなものです。(笑)
ただ、グループカウンセリングの場で、よく発言していたのだけは覚えています。
1年経った時に、廣瀬先生から「卒業です。」と言われました。
「え?まだ全然治っていないのに、、、。
でも、音読は嫌いだから、早く卒業できるのはありがたい!」
という、極めて不純な理由で卒業させていただきました。(笑)
(現役生はみんなの前で音読をして、吃音の観察をするのです。)
まじめに通っているかたには、本当に申し訳なかったと思います。
その後は修了生として、現役生の話を聴かせていただく側にまわり、
少しずつカウンセラーとしての学習が始まります。
2013年から教室の代表になり、2015年からサブカウンセラー、2016年からカウンセラーになりました。
実は、そのころから音読でも、どもらなくなってきました。
数年後に改善することを見越して卒業させてくれた、廣瀬先生の洞察力はすごいものがあります。
これは、先に変容があり、後になって吃音の改善が始まるということなのですが、
私がどこかで変容していたのを、見抜かれていたのですね。

カウンセリングの内容。
さて、肝心なカウンセリングの内容についてですが、これは言葉で表すことは非常に難しいです。
ただ、先生のお言葉でカウンセリングを象徴しているものがいくつかあります。
「いつも自分の吃音だけが一番大事で、それだけに囚われていたのでは何も変化はおこらないのです。」
吃音者は、どもるのを隠したい。
「自分をよく見せることが一番大切」では、変容はなく、相手への思いやりとか、他にもっと大切なものがあることに気づかなければ
吃音の変化もないということです。
「一人で読むとどもっても、みんなと読むとどもらない。
これは、あなたがたの吃音は身体の障害ではないということです。
身体の障害なら、どんな状況でもどもるはずですよね。
身体の障害でないのなら、改善する可能性はあります。」
廣瀬カウンセリンは40年近くの歴史がありますが、当時、吃音は身体(発声器官)の障害だと考えられてきました。
だから、ほとんどの治療家が言語訓練で治そうとしたのです。
今では、ほとんどの専門家が、吃音は心理的な条件反射だと認めていますが、当時、この理論は画期的だったと思います。それだけ、先見の目があったということでしょう。
発達性吃音の場合、遺伝と言われていますが、それは幼児の場合で、成人になるとほぼ心理的要因です。
少なくとも発声器官の障害ではありません。(もし、そうならひとり言でもどもるはずですね)
また、吃音は治らないと言っている学者や臨床家が多数を占める中で、治ると言っていた廣瀬カウンセリングは異端な存在です。
しかし、40年継続して吃音の改善者を輩出し続けていることは、事実です。
では、なぜ広く世間に認知されていないか?ということですが、
廣瀬先生はカウンセリングの実践(臨床)を重視されていたので、学術的な研究をほとんどされていなかったからでしょう。
廣瀬カウンセリングが心理療法として体系化されていないのは残念なところです。
「きついことを言いますが、吃音者との会話が面白くないと感じています。
なぜなら、自分のどもりのことばかり考えていて、相手のことを思いやらない会話になるからです。」
これは、グループカウンセリング中に現役生同士の会話が、かみ合わない時におっしゃった言葉です。
私の経験からしても、吃音で悩んでいる人は会話が自分事にとらわれて
相手の気持ちを察していない場合が多い印象です。
勿論私もそうでしたし、今もどうかは分かりませんが、
少なくとも以前よりは、人の話を聴けるようになっています。
最近の臨床では、吃音者は「自己注目」(自分に注意を向ける)が強いと言われていて「外部注目」(自分の外に注意を向けること)が、必要だと言われています。この「外部」のなかに「相手」も入ります。
「正しい答えを言おうとしなくていい。
今、浮かんだことをありのままに話してほしい。」
私達は、学校教育で正しい答えを出すのが良いことだと教わってきました。
その結果、自分が今感じていることよりも、正しい答えを頭で考える癖がついています。
カウンセリングに来られるかたは、ほとんどがこのタイプです。(結構高学歴のかたが多いです。)
カウンセリング中に感じたことを訪ねても、ほとんど何も出てこない。
逆に言うと、感じたことが湧き出てくるようになると、変容があり、改善が始まります。

「感性を高めていくことが大事。
美しいものを美しいと、ハッと気づくこと=人のこと、自分のことにも気づく
=感性を高める→内臓感覚(吃音)の自覚→自然治癒力→改善」
これもカウンセリングに来られるかたに、最近美しいと感じたものはありますか?
と質問しても、答えがない場合が多いです。
普段から、風景やものを見ない、目的を持ったものの見方しかしていなくて
美しさに対する感覚が足りない人が多い印象です。
ただ、美しいものは感じるのが楽しいけど、吃音を感じるのは楽しくないですよね。
それに対しては、こう仰っています。
「美しいと感じることは簡単で、プラスの感情。これに対し、内臓感覚的刺激(吃音時の身体の観察)は、いやなことなので難しい。
隠れている、隠している、マイナスの感情。この二つのものは同じものだが、後者の方が感じづらい。
よって、前者を感じることと同じようにすることで。後者の内臓感覚的刺激を自覚するということは、あるがままの自分を受け入れる、ということ。」
難しいですね。(笑)
これは、感じるというとには、楽しいとか苦しいとか区別してはならないということだと思います。
マイナスの感情も、区別しないであるがままを正しく自覚することなんですね。
これは心理学全般に言えることですが、嫌なものを避けようとすると、逆にそれに囚われることが多くなります。
ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)では、これを「体験の回避」といいます。
ここは非常に重要なポイントです。
私が、廣瀬カウンセリングや、自分のカウンセリングの話をすると「どもった時の身体感覚を感じるなんて、つらすぎる」と、言われることがあります。
これは「思考」(不安や嫌な感情)と、「身体感覚」(現実におこっていること)を混同しているからです。
正しく感じれば、つらいことはありません。
また、「真のポジティブとは、ネガティブを味わい尽くすこと」という言葉があります。ネガティブから逃げて、その時だけ不安から逃げても、本質的には改善しないのです。
廣瀬カウンセリングは、心理学の基本に則っている。
いかがでしたでしょうか?他の吃音の療法とは大きく違いますね。
ただ、カウンセリング心理学的に言うと、異端ではなく王道だと思います。
なぜなら、カウンセリングの基本である「来談者中心療法」と、
そこから生まれた「フォーカシング」を基本としているからです。
(廣瀬先生がフォーカシングをどう解釈されていたかは、分かりませんが
内臓感覚を重視されていたことから、かなり近い考えではなかったかと思います。)
修正点。
しかし、廣瀬カウンセリングは約30年前に作られた療法なので、
修正しなければならないところもあります。
例えば、廣瀬先生の本には、吃音は親が子供への言葉の介入することから起きると書いてありますが、
これは、現代では否定されています。
吃音になるきっかけは、遺伝子の異常、脳の接続異常からくる、発話のタイミング障害です。
しかし、これは当時の脳科学や遺伝子学は現代のように発展しておらず、致し方ないと言えるでしょう。
ちなみに、成人の吃音になると、遺伝や体質的な要素よりも、心理的な要素が大きくなりますので、
心理カウンセリングは有効だと言えます。
現在の吃音カウンセリングは、認知行動療法や暴露療法(行動療法)が主で
フォーカシングのように、人の内面にアクセスする療法がほとんどないと思います。
(最近は、それに近い療法として、セルフコンパッションが行われています)
しかし、成人の吃音は心理的要因が大きいので、感情や情緒を高めていくカウンセリングは有効だと思います。
では、感情や情緒(感じること)高めていくカウンセリングとは、
どのようなものでしょうか?
廣瀬先生の著書「教える教育の敗北」以下の記述があります。
「考える」ことより「感じる」こと。
教室に参加したばかりのクライアントの感想。
「話し方教室は、どもりを治す場だから、発声練習をしたり、
言葉が出てこなくなったときに、どうすればいいか教えてくれるところだと思ったのに、
いつも文章を読んで、どんなことを感じたのかを話しています。
僕も何か言わなければと思って、読もうとすると声が出なくなると言ったけれど
、そんなことは小学校の時から分かっていた。
だから、こんなことをしていても治らないので、話し方教室をやめようと考えた。」
カウンセリング初期に皆さんが思うことです。
そのクライアントが、数か月後には、次のように変容します。
「はじめは、感じるということがどんなことか分からずに、とても悩んだものです。
でも最近は、工場のそばに咲いているタンポポを見ても、きれいだなと
感じることが出来るようなりました。
そうしたら、どもりもだんだんとよくなって、自信をもって話せるようになってきたのです。」
これは、何を意味するでしょうか?
廣瀬カウンセリングでは「考えること」より「感じること」を大切にします。これはACTも同じなので、
ACTの理論で説明すると、考えること=思考=言語=不安、なのです。私たちの不安は、頭の中のおしゃべりが原因なのです。
(詳しくは、こちらChatter「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法。と
人間は恐怖を派生させる唯一の動物。関係フレーム理論について。をご覧ください。)
それは、「今ここで現実には起こっていない、頭の中の想像」です。吃音の予期不安は、その典型です。
そして、感じることは、現実と接点を持つことで、不安から現実に引き戻してくれる働きがあります。
吃音の臨床でマインドフルネスが行われるのは、「今、ここ」に心をとどめておく効果があるからです。
この話の「タンポポを見る」のも、マインドフルな行為です。
吃音・クラタリング世界合同会議
私は2018年「吃音・クラタリング世界合同会議」が広島で行われたときに、
廣瀬カウンセリングのメンバーとして、カウンセリングの口頭発表と
実演をさせていただきましたが、他の世界の療法を見ても匹敵するものはありませんでした。
(後で知ったのですが、実はこの時初めて日本の吃音学会でACTの発表があったようです。)

現在の廣瀬カウンセリング。
私は、廣瀬カウンセリングから独立して4年ほどになりますが、カウンセリングの場には、時々お邪魔しています。
去年、東京言友会から独立して、独自のセルフヘルプグループとなりました。
吃音は治らないと言う人が多い中で、改善を目指す貴重な存在です。
また、私の見解からすると、今でこそ「マインドフルネス」や「セルフコンパッション」が行われていますが、
40年も前から、すでにその要素を持っていた、先鋭的なカウンセリングだと言えます。
もっと、多くの人に知られるべき存在だと思います。
興味のあるかたは、お問い合わせください。
廣瀬カウンセリングのホームページ