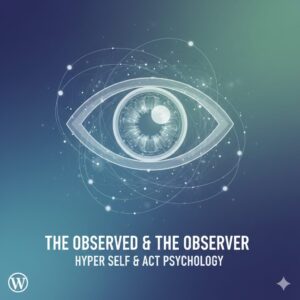「モノマネのときは吃らない」──その理由は、エゴから離れているから。

吃音のある方の中には、こんな経験をしたことがある人も多いと思います。
「モノマネをしているときは、なぜかスラスラ話せる」
「方言のときも吃らないことがある」
実はこれ、単なる偶然ではありません。モノマネのとき、私たちは“ある大切なこと”を自然にやっているのです。
自分(エゴ)から少し離れている
モノマネをしているとき、私たちは「自分として話す」よりも「誰かを演じている」状態になります。
その瞬間、
- 「ちゃんと話さなきゃ」
- 「どう思われるかな」
といった自己評価の意識(エゴ)が、少し後ろに下がるのです。
「自分をどう見せるか」よりも、「その人をどう表現するか」に意識が向く。つまり、“自分”という枠を一時的に手放している状態。
このとき、心も身体もゆるみ、発話の流れが自然になります。
メタ認知──自分を少し外から見ている状態
モノマネ中の私たちは、「自分を演じている自分」を見ています。これは、まさにメタ認知(自分の心の動きを客観的に見る力)が働いている状態です。
普段の会話では、「うまく言おう」「吃らないようにしよう」と自分に同化していますが、モノマネ中は「自分を見ている自分」のポジションに立っています。
ACTで言う“脱フュージョン”の状態
ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)では、このように思考や感情から距離をとることを脱フュージョンと呼びます。
この距離感が、吃音を軽くしてくれるのです。
吃音が出にくいとき、心は「自由」な位置にいる
吃音が強く出るのは、「うまくやらなければ」というプレッシャーの中で、自分を強くコントロールしようとするとき。
一方、モノマネや歌のときは、「失敗してもいい」「ちょっと遊びの感覚」があります。
その自由さこそが、流暢さを取り戻す鍵になります。
日常で活かすには
モノマネが上手くなる必要はありません。
大切なのは、モノマネが教えてくれる「自分から少し離れる感覚」を生活の中でも思い出すこと。
メタ認知を日常で育てる
たとえば、
- 「今、自分は“うまく話そう”と思ってるな」
- 「ちょっと力が入ってるな」
と気づくこと自体が、すでにメタ認知です。
その気づきの瞬間、私たちは少しだけ“観察者”の位置に戻っています。
そこから話す声は、たいてい自然になります。
まとめ
モノマネのときに吃らないのは、
- 自分(エゴ)への執着がゆるみ、
- メタ認知の位置に立っているから。
それは、吃音が改善する方向の心のあり方を教えてくれる自然な体験です。
モノマネは、発声練習というよりも、「自由に話せる心の位置」を教えてくれる先生なのかもしれません。