吃音と日本の教育の深い関係──治らないと言われる本当の理由
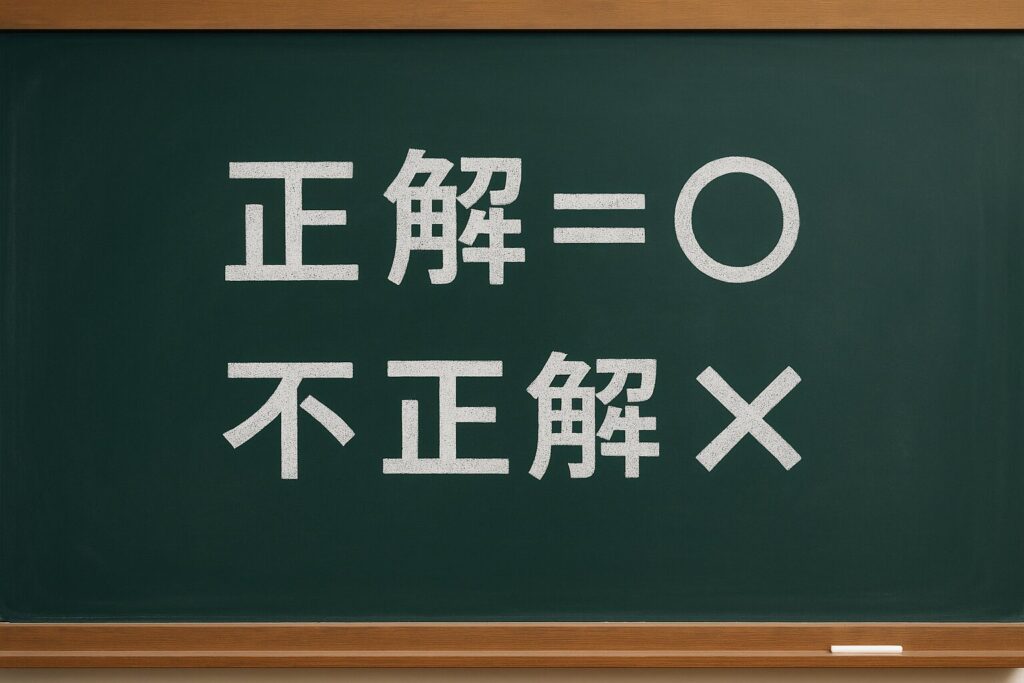
はじめに
私は以前から、吃音を取り巻く環境、とりわけ研究者たちの在り方や研究の方向性に強い違和感を抱いてきました。
吃音に対する社会の姿勢は、どこか日本社会そのものを映し出しているように感じます。
今回は、吃音の世界を入り口に、日本の教育・政治・経済の課題と重ねて、私見を述べたいと思います。
本記事を書くきっかけになった動画はこちら👇
👉【YouTube動画リンク】
ご意見はさまざまあると思いますが、あくまで一臨床家の考えとしてお読みいただければ幸いです。
「バカの壁」と直観の重要性
この動画の中で紹介されていた、養老孟司先生の『バカの壁』。
私のブログでも以前紹介しましたが、これは「自分自身でつくった認識の枠組みの外側に、気づけなくなる」という脳の構造を指します。
🔗 関連記事:バカの壁と吃音──思い込みが邪魔をする瞬間(※内部リンク)
この「枠の外側に出る力」は、いわば直観力や気づきの力。
科学や心理療法の世界でも、こうした「気づき」は近年再評価されています。
マインドフルネスと東洋思想の再発見
現在、吃音臨床でも活用されているマインドフルネスやセルフ・コンパッションは、もともと東洋の瞑想思想にルーツがあります。
ジョン・カバットジン博士が禅をベースに医療分野へ応用したことで、世界中で広まりました。
博士の発想は、「正しい答えを求める教育」の延長にはありません。
それは、「直観的に正しいと感じること」が出発点です。
岡潔が嘆いた「情緒の喪失」と教育の貧困
この「直観」や「情緒」の軽視について、戦後の日本に警鐘を鳴らしていたのが数学者・岡潔(おか きよし)です。
🗣️「人間はまず情緒を育てねばならない。情緒があって、初めて知性が働く。」(岡潔)
岡は、知識や論理ばかりを重視し、自然との共感力や人間らしい感情の深さを育てない教育のあり方を、晩年まで強く批判していました。
私自身の吃音臨床においても、「こころの深さ」「感じる力」を軽視すると、どこかで支援が行き詰まることを痛感しています。
吃音に悩む人に見られる3つの傾向
長年、成人吃音の臨床に携わってきた中で、次のような共通傾向が見られます。
✅ 学歴が高い
✅ 親や教師の期待に従ってきた
✅ 自分の意見や好みを表現するのが苦手
これはまさに、「正解主義」「他者基準」で生きてきた結果といえるかもしれません。
🤔「では、あなたは何をしたいのか」と問われると、戸惑ってしまう方が多いのです。
吃音研究における「治らない前提」とその背景
成人吃音の研究には、「治らない」という暗黙の前提が存在していることが少なくありません。
背景には、研究者自身が吃音当事者であり、かつ、素直で学歴主義的な教育環境で育ってきたという点があるのではないかと感じています。
❗もちろん、研究者個人を否定する意図はありません。ですが、分野横断的な視点や直観的思考が欠けていると感じる場面は多くあります。
日本の教育と「正解主義」の落とし穴
日本の学校教育では、
- 正確に知識を覚えること
- 答えを出すこと
が重視され、「自分で問いを立てる力」「別の見方をする力」は育ちにくい仕組みになっています。
クライアントからよく聞かれる質問:
「正解は何ですか?」
「このやり方で合ってますか?」
こうした価値観こそが、吃音の改善や自分らしい生き方を妨げる要因の一つです。
岡潔や小林秀雄、養老孟司といった多くの知識人も、この問題に早くから警鐘を鳴らしていました。
政治・経済も同じ構造を抱えている
吃音だけではありません。日本社会全体が「正解主義」に縛られているように見えます。
財務省をはじめとする官僚機構には、
- 教科書の知識を信じ
- 前例や慣習を疑わず
- 上に従う文化
が根付いています。
これは、教育の産物です。
科学偏重がもたらす視野の狭さ
近年の吃音研究では、脳科学や遺伝の視点が注目されています。
確かに重要ですが、それだけを「唯一の真実」としてしまうと、環境・心理・行動などの視点が切り捨てられてしまいます。
👶 赤ちゃんにはどもらないが、少し大きくなって、その子供に「今日はおじさんどもらないね」と言われた瞬間からどもり始める…
このようなエピソードを、脳や遺伝だけで説明できるでしょうか?
また、このような視点から吃音を研究することはほとんどないように思います。
吃音界隈の閉鎖性にも課題がある
私自身、心理カウンセラーですが、医学・言語聴覚学など、複数の分野にも興味を持って学んでいます。
しかし、吃音界隈には学際的な対話を避ける傾向も見受けられます。
今まで、実際に勉強会や意見の交換を提案しても、ほとんどスルーされることが少なくありませんでした。
このような「専門分野に閉じこもる姿勢」が、吃音支援全体の進化を妨げているように感じます。
おわりに:岡潔のことばを胸に、枠の外へ
吃音を取り巻く世界は、日本社会の縮図のようです。
- 正解主義の教育
- 硬直化した研究姿勢
- 閉じた専門コミュニティ
これらすべては、私たちが見直すべき「構造」そのものかもしれません。
岡潔はこう語りました。
「教育とは情緒を育てること。情緒のない知性は危険である。」
吃音支援においても、まず人間らしさや、感じる力、自然な直観を取り戻すことが何より大切だと、私は感じています。
異なる分野を横断しながら、広い視点で吃音を捉える。
そんな実践を、これからも大切にしていきたいと思います。


