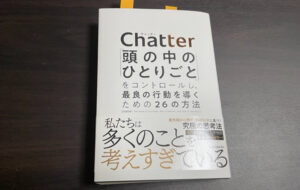吃音と「沈黙に耐える力」──ACT・関係フレーム理論から考える
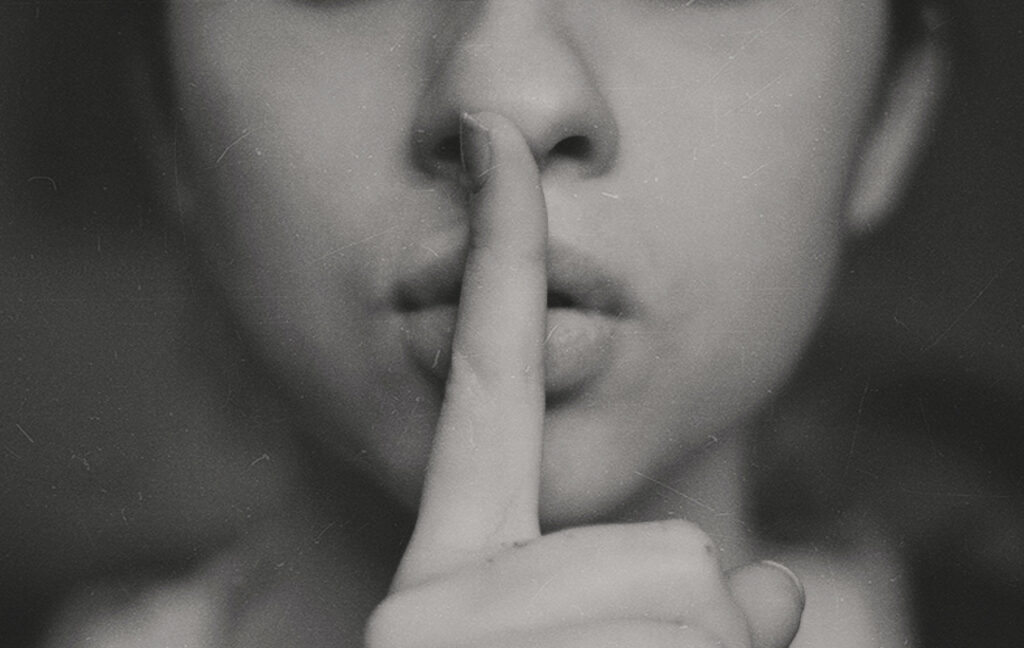
UnsplashのKristina Flourが撮影した写真
今年初めての投稿になります。
いつもマニアックな内容にお付き合いいただき、本当にありがとうございます(笑)。
今回は、前回ご紹介した「関係フレーム理論」やACT、そして私が学んできた吃音カウンセリングの視点から、「沈黙に耐える力」の大切さについてお話ししたいと思います。
吃音と「沈黙の恐怖」
吃音者にとって「沈黙」は怖いものです。
言葉が出てくるまでのあの「間(ま)」は、何ものにも代えがたい不安や恐怖を伴います。
しかし、今回取り上げる「沈黙」は、それとはまったく意味が異なります。
「思考=言語」──関係フレーム理論からの視点
前回の記事でご紹介したように、関係フレーム理論では、悩みや嫌なことを思い出すのは「思考」であり、それは「言語」であると考えられています。
これは、行動分析学という心理学の分野で研究され、多くの専門家に受け入れられている考え方です。
悩みの正体を突き詰めていくと、それは「ボリュームゼロのおしゃべり」とも言えるでしょう。
思考(おしゃべり)は両刃の剣
もちろん、「おしゃべり(思考)」そのものは悪ではありません。
思考によって、私たちは記憶し、判断し、空想し、計画し、人生を豊かにしています。
しかしその一方で、
- 過去のつらい出来事を再体験する
- 自分と他人を比較する
- 自己批判・評価に陥る
- 不要な課題を自らに課す
など、ネガティブな側面にもつながってしまうのです。
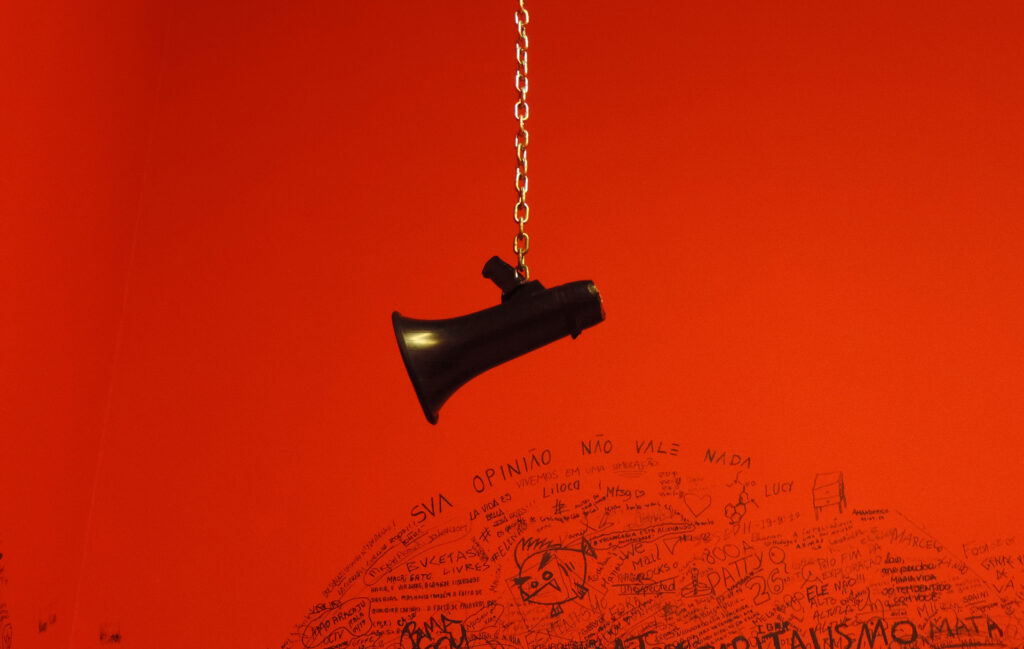
暴走する思考を止めるもの──マインドフルネス
では、この「おしゃべり」が暴走し始めたとき、どうすればよいのでしょうか?
それが「マインドフルネス」です。
マインドフルネスには、「頭の中のおしゃべり」をいったん静める効果があります。
夕日の例:思考が入り込む瞬間
以前も書きましたが、美しい夕日を見て純粋に感動しているとき、私たちは何も考えていません。
しかし、しばらくすると「スマホで撮ろうかな」「SNSに投稿したらいいねがつくかな」と思考が入り込んできます。
その瞬間、私たちは「夕日を見ているつもり」であっても、実はもう見ていないのです。
網膜には映っていても、意識は「今・ここ」から離れているのです。
マインドフルネスは、この意識を「今・ここ」に戻す練習です。
マインドフルネスの定義(ACT的理解)
マインドフルネスとは、
「アウェアネス(気づき):外部から入る情報と、内部から湧いてくる情報の両方に、自由に注意を向けられる状態」
「アクセプタンス(受容):それらの情報に対して、批判したり先入観で決めつけたりせず、ありのままを受け止める姿勢」
と定義されています。
この「先入観で決めつける」ことこそが、ACTの視点で言うところの「思考」「マインド」「おしゃべり」なのです。

沈黙に耐えられない現代──TikTokとイントロの話
最近では、TikTokで流行る曲がヒットする傾向にあります。
あるミュージシャンが「イントロが長いと聴いてもらえない」と話していました。
長いイントロ=退屈、という「判断」によって、音楽の本質にたどりつく前に聴かれなくなってしまうのです。
「沈黙に耐えること」が芸術を理解すること
私が学んだ吃音カウンセリングのテキストには、こんな言葉があります:
「絵や音楽がわかるということは、沈黙の力にたえる経験をよく味わうことにほかなりません」
一見すると、音楽を聴くことと「沈黙」は矛盾しているように思えますが、
思考を入れずに音楽を聴くという行為は、まさに「沈黙の力に耐える」ことだと感じます。
吃音の観察には「思考」から離れる修練が必要
吃音の観察もまた同じです。
思考を入れずに、ただ観るというのは相当な修練が必要です。
「すみれの花という言葉が諸君の心のうちに入ってくれば、諸君はもう目を閉じるのです。それほど、だまって物を見るのは難しいことです。」
という言葉がありますが、これは「観察」の本質を突いています。
セラピーにおいては、この「難しさ」を自覚することが第一歩です。
思考を外して観察できたとき、何が起こるか?
「思考」によって生まれる恐怖や不安は、完全には消えませんが、最小限に抑えられます。
また、**「気づき」や「直観」**が生まれやすくなります。
気づきは、過去の思考とは違い、意識を通さずに新しい何かを一瞬で理解するような体験です。
これが「変容」につながり、吃音への捉え方や症状の変化につながっていくのです。
フォーカシングと「言葉にならない感覚」
「フォーカシング」という心理療法では、まだ言葉になっていない感情や感覚を、身体との接点を通して感じ、
それを優しく受け止めることで「ありのままの自分」を受け入れることを目指します。
この「言葉になっていない」感覚こそが、ACTの立場では「思考」ではなく「観察する自己」や「純粋な気づき」なのです。
まとめ:観察ができるようになると、変化が訪れる
吃音者が、
- 予期不安に襲われているとき
- 実際にどもっているとき
- 後悔に苦しんでいるとき
このようなとき、ほとんどの場合「観察」ができていません。
ということは、観察ができるようになることで変化が生まれる可能性がある、ということです。
私自身も、この実践によって変容が起こり、吃音症状も軽減しました。
同じような変化を経験している方は、私の周囲にも多くいらっしゃいます。
もちろん、現時点では科学的エビデンスが乏しいという課題はあります。
これは一カウンセラーの立場で解決できる問題ではありませんが、だからこそ、私は日本吃音流暢性学会に入会し、
今年の学会での発表を目標にしています。
(この記事は、2023年1月に投稿した記事をリニューアルしたものです。この年、学会でACTによる吃音の臨床について、発表させていただきました。)