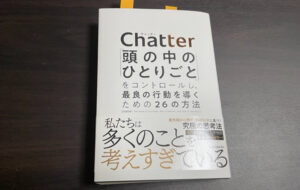人生の「価値」を明確にすることで吃音は変わる──ACTが示す本当の回復の道

忙しい日々の中で気づいた「価値の大切さ」
最近は忙しくてなかなかブログを書く時間が取れませんでしたが、久しぶりに落ち着いてパソコンの前に座っています。
今日は、最近とても大切だと感じるようになった「価値の明確化」について書いてみたいと思います。
ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)とは?
ACT(最新型の認知行動療法)には、次の6つのコアプロセスがあります。
① 今、この瞬間との接触
② 脱フュージョン
③ アクセプタンス
④ 文脈としての自己
⑤ 価値
⑥ コミットされた行為
この6つを通して「心理的柔軟性」を育むのがACTの目的です。
私は吃音のカウンセリングの中で、ACTを学ぶ前から①〜④は自然と取り入れていました。
しかし、⑤「価値」と⑥「コミットされた行為」には十分に触れてこなかったのです。
これは私が従来の行動療法をベースにしていなかったためでもあります。
「価値」とは何か──人生のコンパスを持つこと
ACTでいう「価値」とは、自分が本当に求めたいもの・大切にしたいものを指します。
つまり、「どんな人間でありたいか」「どんな行動を続けていきたいか」という人生のコンパスです。
ACTのテキストでは、次のように説明されています。
「価値とは、私たちの心の一番奥にある『願い』です。
自分は、世界や周りの人、そして自分自身とどのように関わりたいかという希望です。」
ACTと従来の認知行動療法(CBT)の違い
従来の認知行動療法(CBT)では、「思考の内容を修正する」ことを目指します。
たとえば、テストで70点を取ったとき、「70点も取れた!」と考えれば前向きになれますが、「70点しか取れなかった」と考えると落ち込みます。
この思考の修正を通して苦痛を和らげるのがCBTの方法です。
一方、ACTは「思考を変える」のではなく、「思考との関わり方を変える」アプローチです。
嫌な思考が浮かんでも、それを無理に消さず、そのままにしておく。
そして、そのエネルギーを「自分の人生を豊かにする行動」に向けていくのです。
苦しみとの関わりを変える──ACTの仏教的背景
この「嫌な感情をそのままにしておく」という考え方は、仏教の「人生は苦しみから逃れられない(四苦八苦)」という思想にも通じます。
ただし、ACTは「苦しみをなくす」のではなく、「苦しみとの関わり方を変える」ことを目指します。
スキーの例でわかる「価値に生きる」ということ
たとえば、スキーが好きな人を想像してみましょう。
寒い場所へ出かけ、長い渋滞に耐えなければなりませんが、それでも「スキーを楽しみたい」という価値があるからこそ行動できます。
「寒さ」や「移動の面倒さ」も、価値に沿っていれば苦痛ではなく「プロセスの一部」として受け入れられるのです。
吃音と「行動の回避」──本当の自分を見失わないために
吃音の方がよく陥るのが、「話したいけれど吃音が出そうだから会うのをやめよう」という行動の回避です。
確かに、その瞬間は安心しますが、「本当は話したかった」という価値に反する行動になります。
その積み重ねが「自分が何を大切にしたいのか分からない」という自己の不一致を生むのです。
セルフヘルプグループで見た「価値」と「コミットされた行為」
私が開業前に所属していたセルフヘルプグループでは、吃音をある程度受け入れた人が、今度は他のメンバーを支える立場に回っていました。
そこには「他者の力になりたい」という自然な価値が生まれ、その思いに基づいて行動する──まさに「コミットされた行為」が実践されていました。
吃音の改善は「目的」ではなく「副産物」
吃音を「治すこと」をゴールにすると、かえってうまくいかないことが多いのです。
しかし、「誰かの力になりたい」「自分の経験を分かち合いたい」という価値を持ち、行動に移すことで心理的柔軟性が高まり、結果として吃音が改善する例を多く見てきました。
吃音の改善は、あくまでボーナス(副産物)なのです。
「価値」に基づく生き方が、自然な言葉を取り戻す
吃音の治療はこれまで、「流暢に話す」か「吃音を受け入れるか」に焦点を当ててきました。
しかし、本当に大切なのは「何を話したいか」「なぜ話したいのか」という内側からの動機です。
それこそが「価値」に基づいた生き方であり、自然な言葉の回復にもつながります。
人生の価値を見つけることから始めよう
価値は人それぞれで、誰かに決められるものではありません。
家族との時間、自然の中で過ごすこと、他者を支えること──どんな価値でも構いません。
時間とともに変化していくものでもあります。
自分が本当に大切にしたいものを見つけること。
それが、吃音の改善だけでなく「しなやかな生き方」への第一歩になるのだと思います。